はじめに
半導体業界では、ムーアの法則に基づきトランジスタの集積度向上が性能とコスト効率を高めてきました。
しかし2nm世代に入り、微細化は物理的限界やコスト増に直面し、従来の手法では性能維持が困難になっています。
そこで注目されるのが「先進後工程(Advanced Packaging)」です。
これはチップの端子形成ではなく、パッケージ自体がシステム性能を左右する新たなフェーズです。
本記事では、先進後工程の技術概要とIntel、TSMC、Samsung、ASEの戦略・強みと競争力を探ります。
先進後工程とは何か
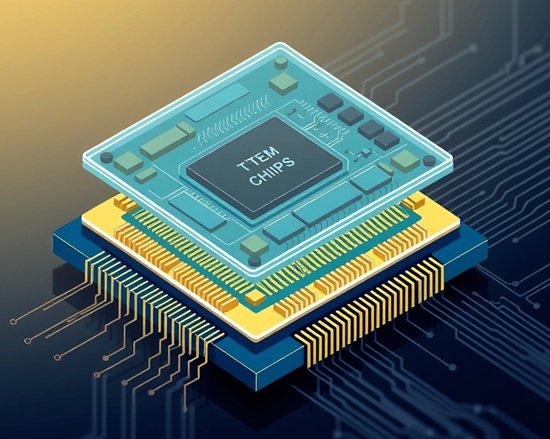
「先進後工程(Advanced Packaging / Advanced Back-end Process)」とは、半導体製造の中でも ウエーハ製造(前工程:Front-end Process) が終わった後に行う 後工程(Back-end Process) の中で、特に従来の組立・封止工程を超えた高度な実装技術を指します。
従来の後工程と先進後工程の違い
- 従来の後工程
・ウエーハを切断(ダイシング)
・チップを基板に実装
・ワイヤーボンディングで電気的接続
・樹脂モールドで封止
- 先進後工程
・3D実装やチップレット統合など、高性能化・小型化・高密度化を実現するための工程
・微細配線やTSV(Through Silicon Via)、RDL(Redistribution Layer)など前工程に近い技術も取り込む
代表的な先進後工程技術
- 2.5D実装
・シリコンインターポーザを用いて複数チップを高密度接続
・例:GPU+HBMメモリの統合 - 3D積層(3D IC)
・TSVを使ってチップを垂直方向に積層
・信号遅延を低減し、帯域を大幅拡大 - Fan-Out WLP (Wafer Level Packaging)
・チップ周囲に再配線層(RDL)を形成してI/O端子を外側に展開
・薄型スマホや車載向けで採用増 - Chipletアーキテクチャ
・大規模SoCを分割し、小さなチップレットを高密度パッケージ内で接続
・設計効率と歩留まりを改善
先進後工程の役割
- 微細化の限界を補う:ロジックの微細化だけで性能向上が難しくなり、パッケージで高性能化
- 高帯域・低消費電力:メモリとロジックを近接配置することで高速通信と省電力化
- 異種集積:CMOSロジック、メモリ、アナログ、光デバイスなどを1つのパッケージに統合
先進後工程の主な技術一覧
| 技術 | 概要 | 特徴 | 主な用途・事例 |
| 2.5D実装(インターポーザ型) | シリコンや有機基板のインターポーザ上に複数チップを配置 | 高密度配線、広帯域I/O、設計柔軟性 | GPU+HBM(例:NVIDIA H100)、高性能サーバ向け |
| 3D積層(3D IC) | TSVを用いてチップを垂直積層 | 信号遅延短縮、省電力、面積削減 | 3D NAND、3D DRAM、将来のロジック+メモリ積層 |
| Fan-Out WLP (FOWLP) | チップを再配線層(RDL)に埋め込み、I/Oを外側に展開 | 小型・薄型、高周波特性良好、コスト優位 | スマホAP、車載半導体 |
| Fan-Out Panel Level Package (FOPLP) | FOWLPを大面積パネル基板で実施 | 生産効率アップ、低コスト化 | IoT機器、スマホ用チップ |
| 2.1D実装 | 高密度有機基板を用いた中間的技術 | 2.5Dより低コストで配線密度は中程度 | ミッドレンジSoC、車載向け |
| Chiplet実装 | SoCを複数の小チップに分割しパッケージ内で接続 | 歩留まり改善、設計柔軟性、異種混載可能 | AMD Ryzen (Infinity Fabric)、Intel Foveros |
| Hybrid Bonding (Cu-Cu直結) | 金属同士を直接接合し、微細な接続を実現 | 極小ピッチ接続、高性能、低消費電力 | HBMスタック、ロジック+メモリ結合 |
| SiP (System in Package) | 複数のチップ・受動部品を1パッケージに集積 | 小型化、システムレベル統合 | スマホRFモジュール、IoT機器 |
主要プレイヤーの取り組みと強み・弱み

「先進後工程(Advanced Packaging)」は、すでに各国の大手半導体メーカーやOSAT(外部委託組立・テスト会社)によって確立・量産されています。
- 確立度トップ3:TSMC、Intel、Samsung(ファウンドリ系)
- OSATトップ2:ASE、Amkor(受託製造で強み)
- メモリ連携:SK hynix、Samsung、Micron
→ 特に TSMC(CoWoS/SoIC/InFO) が業界のリーダーであり、GPU+HBMなどAI半導体の基盤技術を事実上独占的に提供しています。
Intel
- 主力技術:
- EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge):小型ブリッジで2.5D実装
- Foveros:ロジックダイの3D積層
- 強み:
- CPU+先進パッケージの垂直統合
- チップレット設計による柔軟性
- 弱み:
- 歩留まりや量産キャパシティへの不安
- ファウンドリ競争力の揺らぎ
TSMC
- 主力技術:
- CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)=2.5D実装
- InFO(Integrated Fan-Out)=高密度FOWLP
- SoIC(System on Integrated Chips)=3D積層
- 強み:
- 先端ロジック+パッケージの一体提供
- EDA/OSATとの強固なエコシステム
- 弱み:
- リードタイムが長く、需給逼迫リスク
- 高額な投資負担
Samsung
- 主力技術:
- I-Cube(2.5D)
- X-Cube(3D積層)
- Fan-Outパッケージ
- 強み:
- メモリ+ロジックの両面を持つ垂直統合
- HBM実装の実績
- 弱み:
- ファウンドリ市場でTSMCに劣後
- 後工程の量産事例が限定的
ASE(Advanced Semiconductor Engineering)
- 主力技術:
- FOCoS(Fan-Out Chip on Substrate)
- SiP(System in Package)
- 強み:
- 世界最大のOSATとしての量産実績
- コスト競争力
- 弱み:
- 先端ロジックはファウンドリ依存
- プロセス開発力は限定的
技術競争力
先進後工程における競争のポイントです。
- 帯域幅と消費電力の改善:
- AI/データセンター用途で必須
- HBMとGPUの接続で特に重要
- 異種統合(Heterogeneous Integration):
- ロジック+メモリ+アナログ+RFの組み合わせ
- システム全体最適化を可能にする
- 製造キャパシティと歩留まり管理:
- 大規模量産に耐える品質と供給能力が差別化要因
- EDAツール・設計ルールとの連携:
- 設計と実装を橋渡しする技術基盤が重要
先進後工程の重大課題と取り組み
先進後工程(Advanced Packaging)は半導体の性能を大きく左右しますが、その一方ででは重大な課題があります。
歩留まり・信頼性の確保
- 課題
・TSV、Hybrid Bonding、Fan-Outなどでは微細配線や接続部の欠陥が歩留まりに直結します。
・3D積層では1枚の不良チップが全体をダメにするリスクが高い。 - なぜ重要か
・AI/HPC向けチップは高価格・大規模ダイを扱うため、歩留まり低下はコストを直撃します。
・熱ストレスや接合部の劣化による長期信頼性の検証が追いついていない。
熱設計・放熱(Thermal Management)
- 課題
・高密度積層(HBM+ロジック)では発熱が集中し、従来のパッケージ構造では十分に放熱ができません。
・TSVやCu-Cu接続の導入で、熱経路が複雑化し、ホットスポットが発生します。 - なぜ重要か
・AIサーバやHPC用途では消費電力が数百ワット級に達し、放熱不良は性能低下や寿命短縮の要因となります。
・現在も液冷やヒートスプレッダ強化が研究中で、技術的な確率にいたっていません。
供給能力・コスト構造
- 課題
・TSMCのCoWoSなど、先進後工程を担えるラインは世界的に限られ、供給リスクが潜在化しています。
・工程が複雑化することで製造コストが急騰しています。 - なぜ重要か
・実際にNVIDIAやAMD向けCoWoSの生産キャパ不足がAI半導体の供給制約要因になっている。
・先進後工程コストが製品原価の2〜3割を占めるケースも出ており、採算性確保が困難となります。
主な取組み事例
| 課題 | 取組み事例 |
| 歩留まり・信頼性 | TSMC・Intel・Samsung → ウエーハテストの高度化(KGD保証)、Hybrid Bondingの量産化。 |
| 大学(例:東京工業大、台湾大、米国Georgia Techなど) → Cu-Cu接合の信頼性評価、低温接合技術の研究。 | |
| KLA、Applied Materials → AIを活用した欠陥検出・プロセス最適化のソリューション開発。 | |
| 熱設計・放熱 | Microsoft Research / Google / Meta → データセンタ向け液冷・マイクロチャネル実装の実証実験。 |
| 東京大学、ETH Zürich など大学研究機関 → 二相冷却(沸騰冷却)、マイクロ流路冷却の熱流体研究。 | |
| Intel → Foveros実装における冷却設計最適化を継続中。 | |
| 供給能力・コスト | ASE、Amkor、JCET → Fan-Out Panel Level Packaging (FOPLP) の量産ライン投資。 |
| TSMC → CoWoS生産キャパ拡大(台中・竹南工場増設)、SoIC対応ライン強化。 | |
| 研究機関(IMEC、Fraunhoferなど欧州系) → パネルレベル製造プロセスの標準化研究。 |
研究開発・改善事例
各企業、研究機関では以下のような研究開発事例が進行しています。
- TSMC:SoICでのマイクロバンプレス接続開発(熱と歩留まり改善)
- Intel:Foveros Direct(Cu-Cu直結)で低抵抗化
- Samsung:HBM4世代に向けた熱拡散層の研究
- IMEC(研究機関):ガラス基板インターポーザ開発
- 大学連携:AI設計支援によるパッケージ最適化(カリフォルニア大学など)
Wafer-level Known-Good-Die(KGD)/高精度ウエーハテストの強化
- 目的:チップレット/3D積層で「不良ダイがパッケージ全体をダメにする」リスクを下げ、最終歩留まりを改善させます。
- 手法:微細ピッチ・高周波プローブ技術、ウエーハ上での高速試験(電気・IBIST等)、ウエーハ単位での合否判定→良品のみ組立に送る。
- 期待効果:不良流入の低減によりパッケージ歩留まりが大幅改善、工程後半での廃棄コストの削減。
- 成熟度:業界導入が進行中で、先進パッケージに必須の工程になりつつあります。
Cu–Cu(あるいは Cu/SiO₂)Hybrid-bonding の信頼性向上研究
- 目的:微細ピッチでの高密度接続(低遅延・低抵抗)を実現しつつ、接合界面の長期信頼性を確保させます。
- 手法:パッド形状やプロセス条件の最適化、界面材料・酸化防止プロセス、熱サイクル・熱加速寿命試験による評価、低温接合法の研究など。
- 期待効果:接合部のクラックやボイドを抑え、3D積層やHBM結合の歩留まり・耐久性を改善。
- 成熟度:大学・研究機関の論文と企業内開発が活発で、商用転用に向けた信頼性データ蓄積中。
チップ直近のマイクロ流路・液冷(単相/二相)などの革新的冷却技術
- 目的:HBM+ロジック等の高密度積層で発生する局所高発熱(ホットスポット)を除去し、性能と寿命を維持させます。
- 手法:チップ背面やパッケージ内部に微細マイクロチャネルを形成して冷却流体を近接流通させる、あるいはチップ直上での二相(沸騰)冷却構造を実装。
- 期待効果:従来比でピーク温度を大幅低減し、冷却効率向上により高負荷での安定動作が可能。
- 成熟度:研究室・大手クラウド/IT企業の社内実証が進んでおり、今後データセンタ/AIサーバ用途で実装が加速する見込み。
Panel-Level / Fan-Out パネル実装(FOPLP)による量産性・コスト改善
- 目的:ウエーハ単位のFOWLPより大面積パネルでの処理を採用し、歩留まり向上と工程単価低減、量産スケーリングを実現させます。
- 手法:ガラス/有機パネル上でのRDL形成、パネル対応の自動実装設備、レイアウト最適化による工程効率化。
- 期待効果:生産効率と歩留まりの向上により、先進後工程のユニットコスト低減と供給能力増強に貢献。
- 成熟度:市場で採用が拡大中(PLP市場の高速成長予測)、OSATの設備投資も増加。しかしパネル対応での工程立ち上げに課題(設備・ハンドリング)があります。
AI/機械学習を活用した異常検知・プロセス最適化(自動検査・予測保全)
- 目的:工程中の微小欠陥を早期検出して不良流出を防ぎ、工程パラメータをリアルタイム最適化して歩留まりを向上させます。
- 手法:画像検査データやプロセスログを学習して欠陥分類・根因推定を自動化、予測的に設備保守を行うことでダウンタイム削減。
- 期待効果:欠陥検出精度向上(偽陽性/偽陰性の低減)、歩留まり向上、工程変動の迅速な是正によるコスト低下。
- 成熟度:研究と商用ツールの双方で急速に実装が進む段階。多くの装置メーカー・IDM・OSATが導入投資を拡大中。
技術ロードマップ(短期〜中期〜長期)
| 時期 | 主な技術開発 | 狙い | 具体例 |
| 短期 (〜2025年頃) | ・Wafer-level Known-Good-Die(KGD)強化 ・AI検査・プロセス最適化の導入拡大 ・Fan-Out Panel Level Package (FOPLP) の量産拡大 | ・歩留まり改善と供給能力拡大 ・工程コスト削減 | ・TSMC/Intel /AmkorでのKGD工程強化 ・ASE/Amkorのパネルレベル実装ライン稼働 ・KLAなど検査装置メーカーのAI搭載検査 |
| 中期 (2025〜2030年頃) | ・Cu–Cu Hybrid Bondingの信頼性向上と量産拡大 ・マイクロ流路冷却の試作初期導入 ・3D積層(ロジック+HBM)の本格普及 | 高帯域・低消費電力化、熱問題解決 | ・TSMC SoIC、Intel Foverosの量産ライン拡大 ・Microsoftやデータセンタ向け液冷実装開始 ・HBM4世代の量産 |
| 長期 (2030年以降) | ・二相冷却/冷媒直流路の商用化 ・大規模パネルレベル製造での標準化 ・AI主導の完全自律プロセス制御 | ・放熱課題の抜本解決 ・供給能力の飛躍的増加 ・低コスト化 | ・サーバー/HPCでの直冷技術標準化 ・OSAT各社のパネルレベル工場稼働 ・AIによるエンドツーエンド品質制御 |
まとめ
先進後工程は、微細化の限界を補う方法として急速に進化しています。
Intel、TSMC、Samsung、ASEは、いずれも異なる強みを発揮しつつ、帯域幅拡大、消費電力低減、異種統合をめぐって激しい競争を繰り広げています。
重要なことは、「パッケージ=後工程」という固定観念を捨て、システム全体を設計・最適化する視点を持つことです。
材料、熱設計、EDA、信頼性評価など、多様な分野を横断的に理解することで、次世代半導体の競争力を左右することに成るかも知れません。



